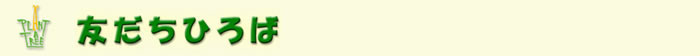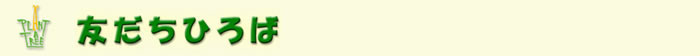|
昔、香港映画にミスターBOOというのがあった。映画館から出たとき「痛快」だった。
痛快の意味は、胸がすくほどの気持ち良さとなるが、それなら、なぜ「痛い」をイメージさせる単語が入っているのだろう。
意味どおりの単語なら「通快」とすれば、快さが通るとなって、読んで字のごとしの単語となったはずである。
「痛」を上にした単語は「痛感」「痛切」などもあるが、下におくと「頭痛」「苦痛」「激痛」などになり、ちゃんと「痛い」に通ずるものがある。
この「痛」を上におくことで示唆することは、漢字の部首を見ればわかる。「しんにゅう」だと「通」るとなるが、「やまいだれ」の場合、その意味の中に「痛」み、きわめて、非常にしみるというものがある。つまり、痛快とは、気持ち良さが体にしみてくるようなこととなる。
能書きはさておき、この痛快な思いをしたりさせたりが人生でおこる日が1日でも多い方がいいと思う。
特に、感受性豊かな幼いころに・・・。
5才の男の子同士8人で山へ入っていく。「そこはヘビが出てくるといけないから行っちゃダメよ」とかいう大人が1人もいないってだけで痛快なのだ。自分たちで「ここは危なそうだ」とか「これは何だろう」とか「ノコギリクワガタが人数分の8匹とれたクヌギの木」とか、それはそれは痛快この上ない日となる。
少し大人になって8才のやんちゃ坊主同士5人でアントニオ猪木がいる新日本プロレスを観に行く。帰り道も、次の日の学校の昼休みでも、コブラツイストをかけ合うほど痛快さが残る。
さらに大人になって10才のワルガキ6人で市営プールへ遊びに行ったら、よその学校のワルガキとプールサイドでケンカになり、途中で飛びこみ教室の先生に止められ「あの10mの高さから6人が6人とも飛びこんだほうが勝ちってことで勝負をつけろ」と言われ、6対2で勝った、あの痛快さ。帰り道、相手にアイスのホームランバーをおごらせて食べたときの痛感さ。
12才のとき、おやじの会社が都市対抗野球で、後楽園球場で行われる全国大会に出場することになり、おやじの会社の4番、後に巨人に入団した山本こうじのホームランが出たときの痛快さ。
僕はたくさんの痛感さを体験させてもらっている。
今の子どもたちにもたくさんの痛感を体験してほしいもんだ。
何かを達成したときの痛感さ。
何かを克服したときの痛感さ。
何かを発見したときの痛感さ。
何かを理解したときの痛感さ。
何かを主催したときの痛感さ。
何かを感謝したときの痛感さ。
何かを縁起したときの痛感さ。
何かを感嘆したときの痛感さ。
何かを一道したときの痛感さ。
何かを決断したときの痛感さ。
痛快な芽となるものは、感受性豊かな幼きときほど豊富にころがっている。
たくさん痛快して、痛快な子になってほしい。
痛快な子が増えたなら、将来は豪快な大人がたくさん増えるだろう。
痛快と豪快に共するものは“笑”に通ず。

ブックドクター・あきひろ |