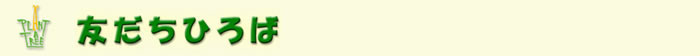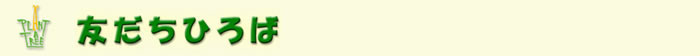|

| 日本初の「ヒグマレクチャー」 |
知床国立公園(しれとここくりつこうえん)のふもとの町、ウトロの小中学校では、去年から日本で始めて道徳の授業でヒグマレクチャーという、もしヒグマに出会ったらどうすればよいかなどを僕たち知床財団(しれとこざいだん)のスタッフが教えることになりました。
なぜウトロの小中学校でこのようなヒグマレクチャーをしなければならないかというと、ウトロの町は国立公園の森に囲まれた町で、森の中にはたくさんの野生動物が住んでいます。もちろんそこには、日本の野生動物では一番強いヒグマもいます。ヒグマは、ふだん森の中で生活していますが、エサをさがしながら移動(いどう)している間にウトロの町へ間違って出てきてしまうことがあります。そのため、小中学校の周りを電気牧柵(でんきぼくさく)という電気のさくでかこってヒグマが入ってこられないようにしたり、ヒグマのかくれられそうな背の高い草を切って見通しを良くしたりしてヒグマが町に出てこないようにしています。でも小中学生が学校への登下校時間にヒグマに出会ってしまうことがあります。そこで僕たちは、どうすればヒグマが町に出てこないかを紙しばいを使ってせつめいし、もしヒグマに出会ってしまったらどうすれば安全にヒグマからのがれられるか実際にヒグマの着ぐるみを着たスタッフと実演(じつえん)してもらいおぼえてもらっています。
このようにウトロの小中学校では、小さい頃から授業で野生動物と共に生きることを教えることによりウトロ住民の一人一人のいしきが高くなると思います。 |
 |
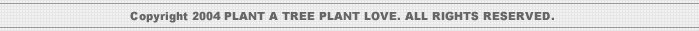
|
|